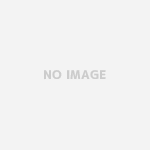なんのかんので4回目となりましたこの企画。これまでヨーロッパの奏者を取り上げてきましたので、ここらでアメリカに目を向けてみます。
ということで今回取り上げるのはアレックス・クラインです。
アメリカの生ける伝説
1964年生まれ。ブラジルで音楽を学び、10歳ではオーケストラの演奏会でソリストとしてデビューしたらしいです。
その後、ブラジル国内の室内オーケストラの重要メンバーとして活動し、第一回目のLucarelli International Competition for Solo Oboe Players で最優秀賞を受賞。1988年にはジュネーブ国際コンクールで多くの賞を受賞(ホリガー以来29年ぶりとのこと)。
1995年に30歳でシカゴ交響楽団の首席奏者となりました。
順風満帆に見えた彼の音楽家人生ですが、残念なことに局所性ジストニアを発症してしまい、手の動きに支障がでるようになってしまいました(発症したのはシカゴ交響楽団に入団して2年目のこと)。
このため、2004年7月にシカゴ交響楽団を去ることとなります。極東ツアー中、チャイコフスキーの交響曲で十分なパフォーマンスを発揮出来なかったため、といわれています(Wikipedia参照)。
その後、音楽学校の教授として後進の指導にあたったり、オーボエのソロ活動や指揮活動を行っております。
そしてなんと2016年6月に再びシカゴ交響楽団の首席奏者として復帰しております(しかもオーディションを経て!素晴らしい!!!)。
私にとっての彼は、バレンボイム時代のシカゴ交響楽団の首席奏者として圧倒的な技術と音楽性で、前任者であるレイ・スティルの印象を良い意味で塗り替えた名奏者です。
あまりアメリカのオーボエ奏者が好きでなかった(失礼)当時でも、アレックス・クラインの演奏は好きでしたねぇ(今はアメリカの奏者は好きです)。
余談ですが、彼が一度辞めたあとのシカゴ交響楽団は、ユージン・イゾトフがバレンボイムの指名で首席奏者になりました。彼はアメリカのオーケストラ初の木管楽器首席奏者となったロシア人です。その後、メトロポリタン歌劇場管弦楽団の首席もつとめ、現在はサンフランシスコ交響楽団の首席奏者だったりします。
オーボエにおける「アメリカン」とは
オーボエは世界各地でそれぞれの伝統があります。楽器の違い(イギリスにおけるサムプレートシステムやオーストリアのウィンナオーボエとか)もそうですが、リードそのものの違いもあります。
オーボエのリードは、葦の茎を削ったものが2枚合わさった形になっています。このあたりの細かい話はちょっと別な機会に書くとして。
最終的にこれを「削る」ことで振動しやすくするんですね。合わさった葦と葦の間に息を通すことでこの二つの葦が振動して音が出るんですけれど、まぁ葦は硬いので、削ることで振動しやすくするわけです。
この削り方にはちゃんとルールというか流儀がありまして。
削りすぎると振動しすぎて音がペラペラになるし、削らなさすぎると振動させるのに空気の圧力が必要になります。唇で振動や開きをある程度調整したりするので、厚過ぎればコントロールするのにも力が必要になってしまい、疲れます。また、少ない圧力では振動しないため、音量や音色などのコントロールもしにくいため、表現が一辺倒になってしまいます。
この「適切な削り方」というのが絶妙に難しいわけで、長い歴史の中である程度流儀がかたまってきているんですね。
もしかするとまたブレークスルーはあるのかもしれないのですが。
現在は大きく2つに分けられます。
- ショートスクレープ
- ロングスクレープ
ここでいうショートとかロングというのは、削ってある面積を指しています。このあたりはGoogleなどで調べてみてください(ロングスクレープのリードを持っていないので、写真無断転用するわけにも行かず・・・)。
私はショートスクレープ使いなのですが、削っていない面が多い事から、音色の変化というよりも押しの強い音色が特徴になります。とくに高音域での伸びが特徴的です。
ロングスクレープは削ってある面積が多いことから、音色の変化がつきやすいようです。高い音から低い音まで自在に操れる印象です。音量もかなり抑えることができるので、一緒に吹くと結構大変です(おれが下手なだけ)。ロングの人たちの弱音ってすげーよほんとに・・・
なお、誤解がある(というか昔おれもしていた)といけないので言っておくと、ロングスクレープは「薄い」わけではありません。むしろリード全体が振動することから、あまり薄いとコントロールできないわけで、扱いが結構難しい印象です(実際、以前試してみたら難しかった)。
アンブシュアももしかしたら違いがあるかもしれませんし、それが楽器の角度にもあらわれる気がします。youtubeなどで調べてみてもらうとわかりますが、ヨーロッパのオーボエ奏者は楽器をの角度が水平に近い人が多い印象です。
しかし、アメリカの奏者はまるでクラリネットを演奏するような角度で楽器を構えている事が多いです。
あくまで印象で、ショートスクレープの人でも様々な角度があるので、これは口の形とかそういうので変わるんだとは思うのですが・・・このあたりはロングスクレープ使いの方どなたか教えていただけるとありがたいです。
で、このロングスクレープを使う方々を「アメリカンスタイル」と一般的なアマチュア奏者は呼んでいます。まぁアメリカン、っていう言い方が正しいのかどうかは議論の余地はある(オーストラリアなんかもロングスクレープ使うといいますよね)のですが。
ちなみにショートとロングの中間のようなタイプもあります(私が使ってるリードはこれに近いかも)。
蛇足っぽいですがもう一つの特徴としてはオーボエのメーカーでしょうか。流派もあるのでしょうが、アメリカではロレーを使う方が非常に多い印象です(あとラウビン)。マリゴを使用している人はあまり知りません(故人ですがサンフランシスコ交響楽団のウィリアム・ベネットはマリゴ使いだったという話を聞いた事があります)。
前述のイゾトフとかって、どうなんだろう?このあたりも知ってる方教えてくださいませ。
魔術師アレックス・クライン(と俺が勝手に呼んでいる)
私の彼の印象は「魔術師」であります。
変幻自在というのが彼の演奏にはふさわしいのではないでしょうか。音量のダイナミクスの幅、音色の引き出しの多さ、多彩なフレージング、どれをとっても素晴らしいです。
アメリカの奏者に対する苦手意識って、音色もそうなのですが、オーケストラの中で「埋もれて聞こえてしまう」(録音の問題もあったり偏見もあるのですが)というのが個人的には一番大きくて、それがオーボエ奏者としてあまり魅力を感じなかったという点だったりします。
ところがシカゴ交響楽団は前任者のレイ・スティルもそうなんですが、あまりオーボエが目立たないという印象はなくて、とても聴きやすい印象でした。
それにさらに多彩な表現力を上乗せしてきたのがアレックス・クラインだと思っています(レイ・スティルの評価が落ちるものではなく、むしろスティルはドイツ物においては未だにトップレベルの表現者だと思っています)。
では彼の魔術師っぷりが堪能できる録音を紹介します。というか、すみません、1枚しか紹介しませんw 他の録音もあるのですが、やっぱり彼を語るにはこの録音だろう、と思うので。
R・シュトラウス オーボエ協奏曲
まぁオーボエ奏者のソロといえば、モーツァルトかこれ、というくらいの超有名曲でございます。しかしこの演奏こそが、彼の「魔術」を堪能するのには最高であると信じています。
冒頭からとにかくゆったりとしたテンポで、じっくりと歌い込まれていきます。シュトラウスの他の作品とくらべても小規模なこの曲ですが、ここまで「静」として曲が進んで行く演奏を他には知りません。
オーボエの多彩な動きで知られるこの曲が、実に丁寧に演奏されていき、1楽章の盛り上がりの部分も、冒頭に作り上げた世界観を変えることなく、まさにこれは「大人な演奏」です。人生を振り返るような、まさに作曲した当時のシュトラウスの心情を理解していたかのような演奏です。
1楽章の最後の方で、冒頭のテーマが戻ってくるあたりは、胸がジーンとしてきます。油断していると泣きそうになる感じで、幸せな響きなのにどこか物悲しいこの感覚は、この曲の録音をいろいろ聴いている自分にとっても、初めて感じたものでした。
ただ1楽章を聴き進めていると、これ2楽章も同じ傾向の演奏なんじゃなかろうか、と思い始めるわけですよ。これって2楽章で変化つかないんじゃないかなぁ、とか。
その心配は杞憂にすぎないことを、冒頭のオーボエの音で叩きつけられます。1楽章とは違った音色とさらなる弱音で、世界観を一変させちゃうんですよこの人!
さらにゆったりとしたテンポになるのですが、この世界観はテンポのせいではなく、彼の演奏そのもので作り上げられている事がよくわかります。
むしろ途中はオケがちょっとだけテンポ煽ったりして、変化を付けてくれるのですが、オーボエのソロに戻るとまた一気に引き戻されます。
といって、甘々なフレージングではないんですよね。一つ一つの音に意味があり、それらが組み合わさることでもっと大きな意思を感じつつ、それは主観的ではなく客観的。
オーボエ吹きとしてこの曲を聴く時は、どうしても「オーボエを聴く」という気構えが起きてしまうのですが、聴き進めていくうちにそういうことは本当にどうでもよくなり、気付けばこの曲そのものに虜にされてしまいます。
2楽章は、まるで薔薇の騎士の最後の三重唱にもつながる感動があります。この曲、本当に、本当にいい曲だなぁ・・・(と聴き直しながら感動している自分)。
2楽章から3楽章へのブリッジ部分のフレーズの長いこと!!!!こういうさりげないところでテクニックを駆使します。それも意味のないことではなく、フレーズを切れさせないために循環呼吸でも使ってる(使ってないのかも)んじゃなかろうか。
3楽章に入っても技巧を前面に押し出すというよりも、フレーズをとても大切にしているのがよくわかります。「動」なのに「静」という、二つを同時に表現している点において、この演奏ってやっぱり特殊なんだよなぁ。うまく彼は自分の演奏をオーケストラに溶け合わせていく瞬間をいくつも作っていて、ソリストが透明になるんですよ。そうすることで、この曲のオーケストラ曲としての側面もうまく聴かせてくれるんですね。
こういう「技」を私は「魔法」と呼びたい。
最後のカデンツァを聴いていると、彼自身も「あぁ、もうこんな素晴らしい曲が、素晴らしい時間が終わってしまう・・・」と後ろ髪を引かれているようで、聴いている私自身も「お、おわってほしくない・・・」と思わされてしまいます。
そしてカデンツァ後からのゆったりした歌い口は、それまでのノスタルジックなものをさらに深めていきます。
あぁ、なんて素敵な時間・・・・と思ったところで、急激に軽快な語り口になり、一気にこの曲は終わります。
これって、薔薇の騎士のラストなんですよね。最後に子供の使用人が出てきて、元帥夫人の落としたハンカチを探して振り回しながら引っ込んで終わる、あの感じ。
つまり、この演奏における最後のオーボエは、それまで長いあいだ歌い込んできていた人とは別人の、未来ある若人であり、それまでのノスタルジックな雰囲気を一変させて、落し物を手にとってくるくる回しながら走り抜けていく、という表現じゃなかろうか、と。
それに気付いた時、この協奏曲の小品が、偉大な作曲家の手による自らの人生振り返りの曲であることを知るのです。若くして書いた英雄の生涯とは違った、作曲家人生の振り返りの曲。
この曲は「協奏曲」という曲の性格上、どうしてもソロオーボエにだけ視点が向きがちなのですが、この演奏はあえてそれを逆手に取ることでこの曲が本来もつ魅力を引き出してくれたのだと思っています。それが出来るのは、もちろん数多くのオペラも手掛けたバレンボイムとのコンビだから、というのもあるでしょうし、アレックス・クライン自身のもつ「魔法」あってのことだと思うわけです。
おそらくこういう演奏は他にはないのではなかろうか、と思っているのですが、この演奏があまり語られないのは、カップリングのホルン協奏曲(クレベンジャーのソロ)がすんごい演奏なことと、この演奏が一聴すると地味に聴こえてしまうということなのかなぁ、と愚行しております。
ただ、この曲を愛する、オーボエを愛する、という方なら、この演奏は必聴であります。是非またこの演奏が数多くの方に聴かれて、コッホやクレメントの演奏のように、聴き継がれていくことを念じてやみません。
・・・熱く語ってしまった(苦笑)・・・。
これからの活躍が楽しみですね
他にもソロのアルバムとかあるのですが、ちょっともうこの1枚だけで私が疲れちゃった(それくらい内容の濃い演奏です!)ので。
でもまたシカゴ響の首席として戻ってきているので、ムーティとのコンビでオーケストラ奏者でもソリストでもどんどん活躍していってほしいな、と思います。
ってか50歳すぎてオーディションでBIG5の首席って、普通にすごいっすよね・・・。
それではまた次回。